はじめに
この記事は、『身近な人間関係が変わる 大切な人に読んでほしい本』(フィリッパ・ペリー著、高山真由美訳、日本経済新聞出版)の第4章を読んで、筆者が印象に残ったポイントを紹介し、考えをまとめたものです。
今回は試験的に、1冊の本について複数記事を書くことにしました。先に第1章、第2章と第3章についての記事は公開済みですので、気になったところだけでも目を通していただけたらと思います。
筆者の解釈が多分に含まれる内容となっている点をご理解ください。また、本書の具体的な内容について触れるため、一部ネタバレを含む可能性があることもご了承ください。
※以下のリンクはAmazonアソシエイトを含む広告リンクです。
本書の概要と要約
本書の第4章では、主に自分自身との向き合い方について論じられています。始めに、私たちが人生に満足できていないのは、幸せを偏重しているからだとし、常に幸せであり続けることはできないが、常に充足感を感じることはできると説いています。
その上で、まず自分の心の動きを観察するところから始め、自分への理解を深めたところで、いかに人生に意味を見いだすかを説明しています。
また、本書全体に通じるテーマ、人間関係の大切さと難しさ、失敗しても見切りをつけずに続けてみることの大切さ、そして結局、自分が変えられるのは自分だけだということが、この章でも繰り返し伝えられています。
敵は自らの中にあり 「内なる批判者」に気づき、観察しよう
私たちは、何かに失敗したと思った時、あるいはもしかすると成功した時でさえも、「自分はまだまだだ」、「自分はダメなやつなんだ」、「こんなんじゃだめだ」と心の中で自分を評価していることがあります。このように自らを否定的に評価する脳内の、いわばもうひとりの自分のようなものを、著者は「内なる批判者」と呼んでいます。
そして著者曰く、私たちは内なる批判者の声に耳を傾けすぎているそうです。習慣の力とは恐ろしいもので、それが客観的に見て明らかにおかしなことでも、日々それに慣れていると、慣れているという理由だけで正しいことのように考えてしまうのです。
本書では、作家になりたいと願っている女性の例が挙げられていました。何不自由なく暮らし、実際に数冊本を出版しているのにも関わらず、あまり売れていないという理由だけで彼女にとって自分は、作家としてまだまだな存在で、人生に不満を抱いているのだとか。
こうして客観的な事実を淡々と述べられると、彼女が作家であることは純然たる事実で、それなのに真の作家になりたいと願う彼女の考えは的外れなように思えます。これが内なる批判者の恐ろしさです。
では、内なる批判者に打ち勝つにはどうすればよいのでしょうか。残念ながら、内なる批判者を完全に排除することはできないそうです。(というか筆者の個人的な意見としては、自己批判は成長を促す側面もあると思うので、そういった意味でも完全に排除してしまうのは好ましくない気がします。)そこで重要なのは、内なる批判者を観察することです。別の言い方をすると、内なる批判者と、その声に耳を傾けそうになっている自分を一歩引いた視点から見るということです。それができれば、内なる批判者の意見は事実とは限らず、正しそうに思えるのもただそれに慣れているからだということを思い出すことができます。
ぜひ覚えておいてください。内なる批判者はもっともらしいことをいう、ただの詐欺師だと。
心 vs 頭 ?
私たちは日々、内的基準と外的基準の両方をもとにして、重要な決断を下しています。
ここで言う内的基準とは、平たく言えば心の声のことで、素直な自分の気持ちとも言い換えられそうです。反対に外的基準は、他者からの見え方や、それを気にする自分の気持ちのことです。つまりは見栄のことですね。これらは心で感じるメリットと、頭で考えるメリットとも対比できます。
さて、では重要な判断を下すときには、どちらを重視すべきなのでしょうか。
本書の基本的なスタンスとしては、人々はもっと内的基準、つまり自分の心の声に従うべきだ。しかし度が過ぎると社会からはみ出してしまうから、外的基準も大事にしましょうね、となります。そして、以下のように続けられています。
頭と心のうち、どちらか一方を選ぶ必要はありません。両方とも大事です。
当たり前すぎて困りますね。つまり、心か頭かという2択ではなく、第3の選択肢「どちらも」を取るべきだという結論です。
筆者がこのトピックを取り上げた理由は、判断する際の軸として内的基準と外的基準があるということを意識していただきたかったから、そして当たり前だけれど、どちらも大切だということを忘れないでいただきたかったからです。
善と悪、真と偽。人は二元論が大好きです。しかし2択に見えるからといって、常にどちらかを選ぶのが正しいわけではないのです。
ネガティブは悪か?
人間は何事にも意味を求める生き物です。穴を掘っては埋めるという、無意味な作業を繰り返すだけで精神が参ってしまうという有名な例からもそのことはうかがえます。
しかし実存主義の哲学者が言うには、人生は無意味で、その事実を受けいれることが私たちのすべきことだそうです。そういわれるとそんな気もしてきますが、だからといって無意味な人生を受けいれられるわけではありません。
そこで著者は、人生に意味を与えるために、私たちはできることを何でもするべきだと言います。そして、そのできることの一つとして提示されているのが、ネガティブな感情、とりわけ虚無感にじっと耐え、受け入れることです。
ネガティブな感情は忌避されがちですが、ネガティブな感情が引き起こされるということは、人生に良くない部分があるということで、逆の見方をすればそれは、人生をまだ良い方向に変える余地があるということを意味します。そういう意味で著者は、ネガティブな感情を、人生を良くするためのコンパスのようにとらえています。
とりわけ著者が重視しているのは虚無感で、これは人生が本来無意味であることに由来する感情です。虚無感を感じたままいることは不快で、多くの人はその不快感を、スマホの画面をスクロールするなどの手段で紛らわそうとします。しかしここで敢えて、虚無感をぐっとこらえて自分の心の動きを観察してみることが提案されています。そうすることで、自分が本当にしたいことや会いたい人に気づくことができるのです。
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございました。
本記事では、『身近な人間関係が変わる 大切な人に読んでほしい本』(フィリッパ・ペリー著、高山真由美訳、日本経済新聞出版)の第4章を読んで、筆者が興味深いと思ったところを紹介しました。
本書は、様々な事例を引きながら、穏やかで優し気な口調で読者に語り掛けるように、人々が陥りがちな悩みを解決するための心構えを教えてくれる本です。
特に以下のような方におすすめです:
- 人間関係で悩んでいることがある
- なぜか人付き合いがうまくいかない
- なんとなく人生に満足できない
- 自分を変えたいけれど勇気が出ない
これは筆者の感想ですが、この本には読者に勇気を与え、人生を変えるきっかけとなる力があると思います。苦しみを抱えたすべての人に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
この記事が、読者の皆様の日々の悩みを解決するための一助になれば、筆者としても大変嬉しく思います。
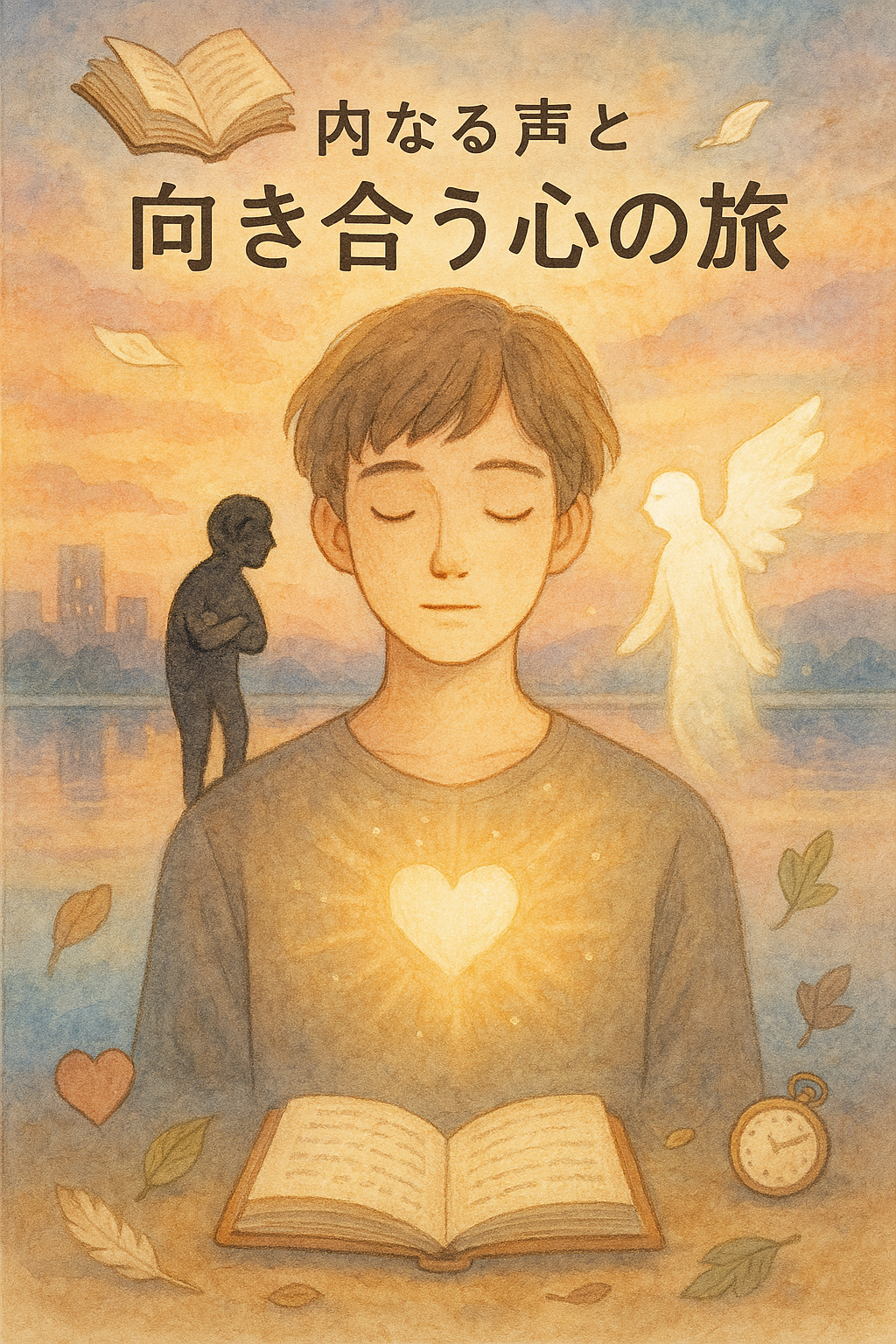


コメント